笑顔を届けるてんかん講師のリンカーン中村です。
「ありがとうを言えないと、誰もあなたを必要としなくなりますよ。」
そんなこと言われたら、ドキッとしますよね。自分で書いてみて、ドキッとしました。笑
でもこれは、あながち間違ってはいないようなのです。
「ありがとう」を言える人と、言えない人に関して、面白い記事を見つけたので、ご紹介したいと思います。
「ありがとう」1日でどのくらい言っていますか?
あなたは、1日の中で何回くらい「ありがとう」を口に出して言っていますか?
少し考えてみてください。
ちなみに、ベルギーの高級チョコレートブランド、ゴディバジャパンが行った調査によると、「ありがとう」を伝えている頻度は、1日平均14.1回だそうです。(参考サイトはこちら)
どうですか?14回。多く感じましたか?少なく感じましたか?
日常生活でありがとうと思える瞬間は、いくらでもあると思います。
・一緒に住んでいる家族、ペット
・職場の同僚やお客さん
・よく行くお店やコンビニの店員さん
・朝ごはん、昼ごはん、晩ごはん
・普段飲んでいる飲み物
・使っているスマートフォン
・毎日のように使う移動手段(自動車、電車、バス、自転車)
・着ている服、履いている靴
おそらくちょっと意識するだけで、14回は簡単に超えてしまうはずです。
「14回も言えてないかも…」という人は、日常生活において感謝の意識が低いのかもしれません。
「ありがとう」を言わないと…
「ありがとう」を伝えないと、色々なデメリットがあるみたいです。
・「ありがとう」を言えない人は、信用・信頼を得られない
・「ありがとう」を言えない人は、周囲のモチベーションを上げるのが下手
・「ありがとう」を言えない人は、敵を作りやすい
・「ありがとう」を言えない人は、いざというときにフォローが得られない
・「ありがとう」を言えない人は、優秀な人材を流出させてしまう
「ありがとう」を言えないだけで、士気を下げ、信用もなく、周りが敵ばかりで、無能な人になりかねません。(極端な例ですが…笑)
要するに、必要とされない人間になってしまうのです。
米国務長官と、駐車場の係員の話からも、それがわかります。
「毎朝、車が次々に到着するとき、最初に出られる位置にどの車を停めるのか、2番目、3番目にどの車を停めるのか、どうやって決めるんだい?」
係員は顔を見合わせて薄く笑い、そのひとりがこう教えてくれた。
「国務長官殿、ま、どういうふうかってぇとですね……ここに着いたとき、車の窓をあけてにっこり笑いかけ、オレらの名前を呼んだり『おはよう。元気にやってるかい?』などと声をかけてくれる人は最初に出られるところっすね。前をじっと見てオレらが何かをしてあげていると気づきもしない人、オレらがいることにも気づいてくれないような人とかは、ま、最後に回されますね」
(引用:「ありがとう」と言わない人は”必ず失う”)
気を使える人かどうかで、周りの人の対応が変わってしまいます。笑
たしかに、仕事においても、プライベートにおいても、「ありがとう」を言える人と言えない人では、印象が全然違いますよね。
僕の今の職場の上司は、「ありがとう」を伝えてくれる人です。任された仕事や簡単な仕事をしても、「ありがとう」と伝えてくれます。それだけで、仕事に対するモチベーションも上がりますし、仕事が楽しくなっていきます。
しかし、以前勤めていた職場の上司は、ほとんど「ありがとう」を言わず、人を小馬鹿にするような人でした。その人の元では、仕事も楽しくなく、職場に行くのも気が重くなっていました。
「ありがとう」一つかもしれませんが、その言葉の持つ意味がとても大きな意味があると思います。
まずは、身近なモノから「ありがとう」
でも「ありがとう」を言うのは、何か気恥ずかしい…。
そんな思いも分かります。僕も以前までは、全然言えない人間でした。笑
しかし、何事も練習です。まずは、あなたの目に止まった”モノ”に「ありがとう」を伝えてみてはいかがでしょうか?
このブログは何で見ていますか?スマートフォンですか?パソコンですか?
一旦文章を見るのではなく、そのデバイスに目を向けてみましょう。使い慣れ親しんだ”モノ”ではないでしょうか?きっとあなたの生活を支えてくれているはずです。
家だとして、職場だとしても、電車やバスの中だとしても、誰にも聞こえないくらいな声でもいいので、伝えてみましょう。
「いつもありがとう」
日頃から意識していないものにこそ、伝えて欲しいと思います。ありがとうを言うのも練習です。練習していけば、スッと言えるようになっていきます。
スマホやパソコンに、ちゃんと伝えることはできましたか?
是非、「ありがとう」を増やして、周りの人にとって、大切な存在になって欲しいと思います。
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
当ブログは、「てんかんを持っている方に元気や勇気を届けたい」という、思いで運営しております。
Twitterでも情報や思いを発信しています。フォローして頂けると嬉しいです!
「癲癇」と「転換」
どちらも読みは、”てんかん”。癲癇という病気の見方や考え方を、プラスな方向へ転換させたいという思いから、”てんかん講師”と名乗っています。
僕自身が、癲癇になって、人生が何度も転換していった。(悪い方へも良い方へも)そんな経験を伝えていきたい。#てんかん #ミレラボ
― てんかん講師 中村真二@6/8東京 6/29浜松,名古屋 (@nakamur809) 2019年4月20日
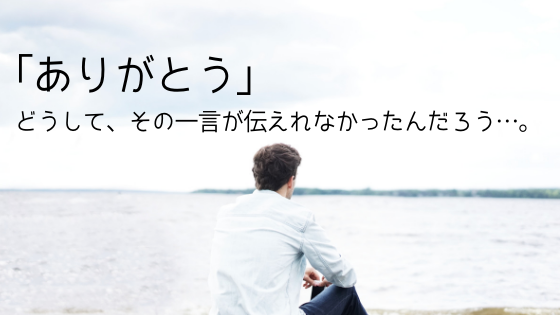



コメントを書く